【完全版】高校生の受験勉強の始め方|効率的な勉強法と生活習慣のすべて
受験勉強って、何から始めたらいいか分からなくて不安になるよね。「周りはどんどん進んでいるのに、自分だけ遅れているかも…」なんて焦ってしまうこともあるかもしれません。でも、大丈夫。この記事では、難しい言葉は一切使わずに、誰でも今日からできる「かしこい勉強のやり方」と「体を元気にする生活のコツ」を、あますところなく紹介します。
この記事を読み終わるころには、まるでゲームの攻略本を手に入れたみたいに、志望校合格までの道のりがはっきりと見えているはず。机に向かう時間だけでなく、毎日の生活すべてが君の味方になります。さあ、一緒に最強の受験生になるための冒険を始めましょう!
まずは計画から!受験勉強のやることリスト
効率のいい受験勉強は、「がむしゃらに頑張る」ことではありません。賢く、スマートに進めるための「作戦」を立てることから始まります。難しく考えなくて大丈夫。たった3つのステップで、君だけの最強の計画が作れます。
①行きたい大学を決めよう
すべての始まりは、ゴールを決めることです。なぜなら、ゴールがなければどこに向かって走ればいいか分からなくなり、すぐに疲れてしまうからです 。勉強は、ゴールのないマラソンに似ています。どこに向かっているか分からないと、モチベーションを保つのはとても難しいでしょう。
しかし、「あの大学に行く!」というはっきりとしたゴールがあれば、それはまるで冒険の地図を手に入れたのと同じです。その瞬間、やるべきことが具体的に見えてきます。例えば、志望校が決まれば、どの科目が入試に必要なのか、どのくらいのレベルの問題が解けるようになればいいのかが分かります 。
これは、勉強の「フィルター」を手に入れるようなものです。自分に関係のない情報に惑わされず、本当に必要な勉強だけに時間とエネルギーを集中させることができます。限られた時間を最も効果的に使うための、これが最初の、そして最も重要な一歩なのです。
また、志望校が決まったら必ず共通テストを受験する必要があるのかどうか確認しましょう。 共通テストの対策にはかなりの時間が必要となります。また、共通テストを対策するか否かで受験すべき模試や今後の計画も変わってきます。そのため、自分の志望校の試験形式は必ず確認するようにしましょう。
②ゴールから逆算して計画を立てる
ゴールが決まったら、次はそのゴールから今いる場所まで、道を逆算して計画を立てていきましょう。受験は、まるでラスボス(最終ボス)を倒すゲームのようなものです。いきなり最強の敵には勝てません。まずは月ごとの「中ボス」、週ごとの「ザコ敵」を倒す計画を立てるのです 。
具体的なステップはこうです。
-
残された時間を計算する: 入試本番まであと何日、何時間あるか計算してみましょう。
-
大きな計画を立てる: 1ヶ月単位で、「この模試までに、この参考書を終わらせる」といった大きな目標を決めます。
-
小さな計画に分ける: 1週間単位で、「今週は数学のこの単元と、英単語を100個覚える」というように、具体的なやることを決めます。
この計画を立てる上で、絶対に忘れてはいけないのが「予備日」を作ることです。計画通りに進まない日や、疲れてしまった時のための「回復の日」を用意しておくのです。一つの失敗で計画全体が崩れてしまうのを防ぐ、大切な安全装置になります。
計画を立てて実行するプロセスは、ただ時間を管理するだけではありません。漠然としていた「受験勉強」という大きな不安を、「今日のタスク」という具体的で管理可能なものに変えることで、心を軽くする効果があります。小さな目標を一つずつクリアしていく達成感が、自信と次へのやる気を育ててくれるのです。
1週間の勉強と生活のモデルプラン
「計画を立てる」と言われても、イメージが湧かないかもしれません。そこで、具体的なモデルプランを用意しました。これはあくまで一例なので、自分の生活スタイルに合わせてアレンジしてみてください。大切なのは、勉強だけでなく、睡眠や食事、休憩といった生活全体を計画に入れることです。
| 時間 | 平日 | 休日 |
| 朝 | 6:30 起床・朝日を浴びる 7:00-7:30 朝食 7:30-8:00 英単語・計算問題 | 7:00 起床 7:30-8:00 朝食 8:00-12:00 苦手科目の集中勉強 (休憩あり) |
| 昼 | 学校の授業に集中 スキマ時間:英単語・課題など | 12:00-13:00 昼食・休憩 13:00-17:00 過去問演習・復習 (休憩あり) |
| 夜 | 17:00-19:00 部活 or 復習 19:00-20:00 夕食・休憩 20:00-22:00 その日の復習・問題演習 | 17:00-19:00 自由時間・運動 19:00-20:00 夕食 20:00-22:00 1週間の復習 |
| 寝る前 | 22:00-22:30 入浴・リラックス 22:30-23:00 暗記ものの確認 23:00 就寝 | 22:00-22:30 明日の準備 22:30-23:00 読書など 23:00 就寝 |
③自分の「今」の力を知っておこう
計画を立てる上で欠かせないのが、自分の現在地を知ることです。そのために最も有効なのが、定期的に模試を受けることです。
模試は、勉強の「健康診断」のようなもの。自分の学力のどこが元気で、どこに栄養が足りないのか(苦手な分野)を正確に教えてくれます。結果が悪くても落ち込む必要は全くありません。それは、これからどこを重点的に強くすればいいのかを教えてくれる、大切なヒントなのです。
さらに、模試にはもう一つ重要な役割があります。それは、試験本番の「リハーサル」です。試験という特別な環境で、時間配分をどうするか、緊張とどう向き合うかといった、知識だけではない「本番力」を鍛える絶好の機会になります。ただ学力を測るだけでなく、本番で最高のパフォーマンスを発揮するための練習として、模試を積極的に活用しましょう。
勉強の効率を上げるすごいテクニック5選
計画が立てられたら、いよいよ勉強の実践です。ここでは、ただ時間をかけるのではなく、かけた時間以上の効果を生み出すための、すごいテクニックを5つ紹介します。
①まずは基本を完璧にする勉強法
難しい応用問題に挑戦したくなる気持ちは分かりますが、焦りは禁物です。難しい問題は、まるでビルのてっぺんのようなもの。土台である「基本」がグラグラだと、絶対に上まで積み上げることはできません。
まずは教科書や基本的な問題集を使って、基礎を100%理解することに集中しましょう。応用問題は基礎問題の組み合わせでできています。もし今の単元が難しいと感じたら、それはその前にもっと基本的などこかでつまずいているサインかもしれません。急がば回れ。盤石な土台を作ることが、結局はゴールへの一番の近道なのです。
この方法は、自信を育てる上でも非常に効果的です。基礎的な問題を確実に解けるようになることで、「自分はできる!」という成功体験が積み重なります。この小さな自信が、難しい問題に立ち向かうための大きな勇気になるのです。
②記憶に残る「繰り返し」復習のコツ
一度覚えたことを忘れてしまうのは、人間の脳にとってごく自然なことです。大切なのは、忘れることを前提に、「思い出す」練習を繰り返すことです。
ここで一番効果的なのが、「アクティブ・リコール(積極的な想起)」という方法。これは、教科書やノートをただ眺めるのではなく、一度閉じて「えーっと、あれは何だっけ?」と自分の頭の中から情報を引っ張り出そうとすることです。この「うーん」と考える時間が、記憶を強化する脳の筋トレになります。
また、復習は一度に長時間やるよりも、短くても回数を多くする方が効果的です。例えば、「授業の直後に1分」「家に帰ってから15分」「寝る前に5分」といったように、こまめに繰り返すことで、記憶はより強固に定着していきます。特に、睡眠には記憶を整理整頓する働きがあるため、寝る前の復習は非常に効果が高いと言われています。
記憶は脳をしっかり使わないと定着しずらいです。ただ参考書を見るだけでなく、脳が疲労するくらいしっかり脳を使って復習しましょう。最初は大変ですが、アクティブ・リコールは非常に効果的な勉強方法なので、すぐに効果を感じられると思います。
③「スキマ時間」でライバルと差をつける
1日の中には、通学の電車の中、休み時間、お風呂を待つ時間など、たくさんの「スキマ時間」が隠れています。この短い時間を制する者が、受験を制すると言っても過言ではありません。
例えば、電車の中での5分で英単語を3つ覚えるとします。たったそれだけでも、1年間続ければ1000個以上の単語を覚えることができます。まさに「チリも積もれば山となる」です。スキマ時間には、英単語や古文単語、歴史の年号、数学の公式、物理や化学の基本事項など、短時間で区切ってできる勉強がぴったりです。
スキマ時間の勉強は本当に偉大です。私は通学の電車の中でのみ英単語を勉強していましたが、それだけでも単語帳を100周以上は勉強できました。スキマ時間にライバルがスマホゲームで遊んでいる中、自分は勉強することでライバルと大きな差を生み出すことが出来ます。
この習慣のすごいところは、勉強を始めるための心のハードルをぐっと下げてくれる点にあります。「さあ、2時間勉強するぞ!」と意気込むのは大変ですが、「単語を3つだけ」ならすぐに始められます。この小さな成功体験が、一日を通して勉強への意識を途切れさせず、本格的な勉強時間へのスムーズな橋渡しをしてくれるのです。
④得意な科目から始めてやる気アップ
「よし、勉強を始めよう!」と思っても、なかなかエンジンがかからない時がありますよね。そんな時は、苦手な科目からではなく、得意な科目や好きな科目から手をつけてみましょう。
これは、まだ準備運動もしていないのに100メートルを全力疾走するのではなく、まずは軽いジョギングから始めるのと同じです。得意な科目で「解ける楽しさ」を感じることで、脳がウォーミングアップされ、勉強への勢いがつきます。このポジティブな勢いに乗ってしまえば、少し気が重い苦手な科目にもスムーズに取り組むことができるようになります。勉強の順番を少し工夫するだけで、やる気をうまくコントロールできるのです。
⑤過去問を使って本番に強くなる
志望校の過去問は、受験勉強の最終仕上げに使うものだと思っていませんか?それは大きな間違いです。過去問は、できるだけ早い時期(遅くとも高校3年生の夏まで)に一度解いてみるべき、最強の「攻略本」なのです。
過去問を分析することで、敵である入試問題がどんな攻撃(問題形式)をしてくるのか、どんなクセ(出題傾向)があるのかが手に取るように分かります。これにより、「すべてを完璧に勉強する」という非効率なやり方から、「合格点を取るために、何を重点的に勉強すべきか」という戦略的な学習にシフトすることができます。
そして受験が近づいてきたら、本番と同じ制限時間で解く練習を繰り返しましょう。これにより、時間配分の感覚を体に染み込ませ、本番で焦らず実力を発揮する訓練ができます。過去問は、ただの力試しではなく、合格への最短ルートを教えてくれる最高のナビゲーターなのです。
勉強を支える!毎日の生活でできる工夫
受験は学力だけで戦うものではありません。最高のパフォーマンスを発揮するためには、心と体のコンディションを整えることが不可欠です。これから紹介する生活習慣は、「勉強の休憩」ではなく、「勉強の一部」だと考えてください。
①脳を休ませる睡眠のルール
テストが近づくと、つい睡眠時間を削って勉強してしまいがちですが、それは最も効率の悪い方法の一つです。脳にとって睡眠は、日中に学んだ情報を整理し、記憶として定着させるための大切な「セーブ時間」なのです。セーブせずにゲームの電源を切ったらデータが消えてしまうのと同じで、しっかり寝ないと、せっかく覚えたことも脳に残りません。
高校生は、毎日7時間から8時間の睡眠を目指しましょう。そして、質の良い睡眠のために、寝る1時間前にはスマートフォンやパソコンを見るのをやめるのがおすすめです。画面から出るブルーライトは、脳を「まだ昼だ!」と勘違いさせてしまい、寝つきを悪くする原因になります。ぬるめのお風呂にゆっくり浸かってリラックスするのも効果的です。
②集中力が続くごはんの食べ方
脳も体と同じように、食事からエネルギーを得て活動しています。特に、朝ごはんは非常に重要です。寝ている間に空っぽになった脳のガソリンタンクを満タンにし、1日の集中力を高める大切な役割があります。
3食を規則正しく、バランスよく食べることが基本です。カルシウムやマグネシウム、レシチンといった栄養素は、集中力や記憶力をサポートしてくれます。一方で、お菓子やジュースなど糖分の多いものは要注意。一時的に元気が出たように感じても、その後急激に血糖値が下がり、強い眠気や集中力の低下を引き起こすことがあります。安定したパフォーマンスのためには、安定したエネルギー補給が欠かせません。
③体を動かして頭をスッキリさせる
ずっと机に座って勉強していると、だんだん頭がぼーっとしてくることはありませんか?そんな時は、思い切って体を動かしてみましょう。軽いウォーキングやストレッチなどの運動は、気分転換やストレス解消になるだけでなく、脳の働きを活発にする効果があります。
体を動かすと、脳内の血流が良くなり、新鮮な酸素が供給されます。また、やる気を引き出すドーパミンという物質が分泌されることも分かっています。たった5分から15分の散歩でも、よどんでいた頭の中の空気が入れ替わり、驚くほどスッキリします。運動は、勉強の効率を上げるための積極的な戦略なのです。
④朝型生活で本番に体を合わせる
大学入試は、ほとんどが午前中に始まります。夜遅くまで勉強して朝寝坊する「夜型」の生活を送っていると、本番で最も頭を働かせたい時間に、脳がまだ眠っている状態になってしまいます。
そうならないために、普段から試験本番の時間に合わせて起きる「朝型」の生活に切り替えていくことが大切です。特に、休日も平日と同じ時間に起きるように心がけることで、生活リズムが安定します。朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を浴びると、体内時計がリセットされ、気持ちよく一日をスタートできます。自分の体を本番モードにチューニングしていくイメージで、生活リズムを整えていきましょう。
やる気が出ない…そんな時のためのヒント
どんなに計画を立てても、どうしてもやる気が出ない日はあります。そんな時は、自分を責めずに、これから紹介するヒントを試してみてください。ちょっとした工夫で、心はまた前を向けるようになります。
①勉強する場所を変えて気分転換
自分の部屋には、ベッドや漫画、ゲームなど、誘惑がたくさんあります。集中できない時は、思い切って環境を変えてみましょう。学校の自習室や地域の図書館、静かなカフェなど、勉強専用の場所に身を置くことで、「よし、やるぞ!」というスイッチが自然と入ります。
周りで他の人たちが真剣に勉強している姿を見ることも、良い刺激になります。「自分も頑張らなくては」という、適度な緊張感が生まれるのです。環境は、人の気持ちに大きな影響を与えます。やる気が出ないのは、君のせいではなく、環境のせいかもしれません。
②スマホは「勉強の敵」と心得る
スマートフォンは、現代の受験生にとって最大の敵かもしれません。メッセージアプリの通知が「ピコン」と鳴るたびに、せっかくの集中力はプチッと途切れてしまいます。そして、一度途切れた集中力を元に戻すには、思った以上に時間とエネルギーがかかるのです。
勉強中は、スマホの通知をオフにするのはもちろん、できればカバンの中にしまったり、別の部屋に置いたりして、物理的に距離を置くのが最も効果的です。「ちょっとだけ息抜きに」と思ってスマホを触るのも、脳を休ませるどころか、逆に疲れさせてしまうことが多いので注意しましょう。
③勉強をゲームみたいに楽しむ工夫
単調になりがちな勉強も、工夫次第でゲームのように楽しむことができます。ポイントは、「目標の見える化」と「ご褒美」です。
例えば、「この問題集を30分で5ページ進める!」というように、自分でミッションと制限時間を設定します。そして、見事クリアできたら、「好きなお菓子を一つ食べる」「好きな曲を1曲聴く」といった小さなご褒美を用意するのです。
覚えた単語の数だけシールを貼ったり、終わった問題集を積み上げてみたりと、自分の頑張りを「見える化」するのも効果的です。勉強をクエストのように捉えることで、達成感が生まれ、次のミッションへの挑戦意欲が湧いてきます。
これはNG!高校生がやりがちなダメ勉強法
最後に、一生懸命やっているつもりでも、実は効果が薄い「ダメな勉強法」を3つ紹介します。もし当てはまっていたら、今日からやり方を変えて、貴重な時間を無駄にしないようにしましょう。
①きれいなノート作りで満足する
色とりどりのペンを使って、教科書の内容をきれいにノートにまとめる。それ自体は悪いことではありませんが、その作業だけで「勉強した!」と満足してしまうのは非常に危険です。
それは、料理のレシピをきれいに書き写しただけで、一度も料理をしていないのと同じです。本当に力がつくのは、その知識を使って実際に問題を解いてみた時だけ。ノートは、後で自分が見返して分かれば十分です。ノート作りに時間をかけるよりも、その時間で問題を1問でも多く解く方が、何倍も合格に近づきます。
②計画を詰め込みすぎる
やる気に満ちている時ほど、1日のスケジュールを勉強でパンパンに詰め込んでしまいがちです。しかし、余裕のない計画は、必ずどこかで破綻します。
お弁当箱にごはんを無理やり押し込むと、フタが閉まらなくなって中身がこぼれてしまうのと同じです。体調を崩したり、急な用事が入ったり、思ったより問題が難しかったりと、計画通りにいかないことは必ずあります。そんな時、余裕のない計画だと「もうダメだ」とすべてを投げ出したくなってしまいます。必ず、予定が遅れた時に調整できる「予備日」や、何もしない時間も計画に組み込んでおきましょう。
③睡眠時間をけずって勉強する
これは、最もやってはいけないNG勉強法です。テスト前になると、多くの人がこの罠に陥りますが、睡眠時間を削ることは、百害あって一利なしです。
睡眠不足の脳は、スマートフォンの充電が10%しかない状態で、最新のオンラインゲームをしようとするようなものです。すぐに動きがカクカクになり、フリーズして、まともに機能しません。集中力も思考力も記憶力も、すべてが低下した状態で勉強しても、効率は最悪です。前日の夜に1時間多く勉強するために睡眠を削るより、しっかり寝て、翌朝スッキリした頭で30分勉強する方が、はるかに効果的なのです。
まとめ
どうだったかな?受験勉強は、暗くて長いトンネルをひたすら一人で歩くようなものではありません。正しい地図(計画)とコンパス(勉強法)、そして元気な体があれば、必ず光の見えるゴールにたどり着けます。
大切なのは、特別な才能ではなく、正しいやり方を知り、それをコツコツと続けることです。今日紹介したたくさんのヒントの中から、まずは一つでもいいので、今日から試してみてください。その小さな一歩が、未来の君を大きく変えるはずです。
君の頑張りを、心から応援しています!
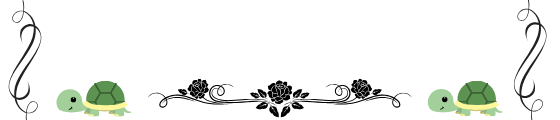
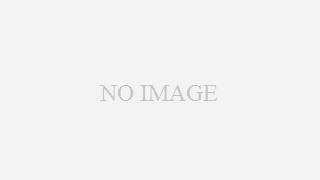

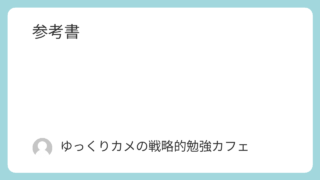
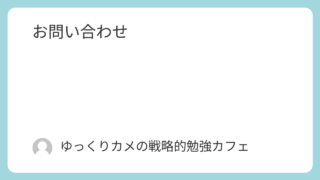

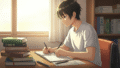
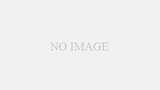
コメント